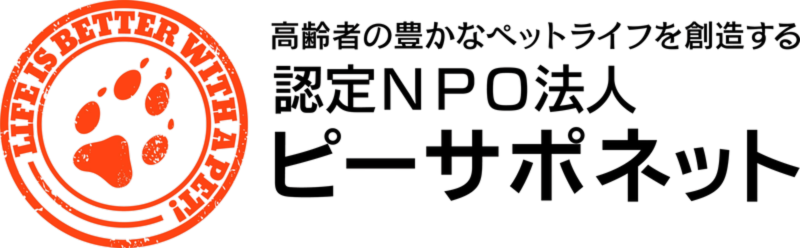ペットの相続専門家とは
飼い主に“万が一”があっても、ペットが安心して暮らせるように備える。ペットの相続専門家は、そのための設計から手続き、見守り体制づくりまでを支援するプロです。弁護士・司法書士・行政書士・動物法務に詳しいFPなどがチームで関わることも多く、飼い主の想いを法的に実現しつつ、受け入れ先や費用の管理まで含めて現実的なプランに落とし込みます。
対応範囲
ペットの飼養契約、負担付遺贈や遺言作成、公正証書の手配、見守りや死後事務委任、ペット信託の設計、受託者・後継受託者の選任、費用(飼養資金)の管理設計、緊急時の引き取り先の確保などを包括的に行います。
依頼するメリット
家族や友人に「頼むね」と口約束するだけでは、引き受ける側の負担や費用の出どころが曖昧になりがちです。専門家は法的効力のある書面で“誰が・どれだけ・いつまで”を明確化し、トラブルや飼育放棄のリスクを下げます。
日本の法制度の基本をやさしく整理
ここでは難しい用語を使いすぎず、実務でよく出会う疑問を軸に整理します。ポイントは「ペットに直接お金を渡すことはできない」という前提と、「代わりに人に義務を負わせる仕組みを作る」という発想です。これを理解すると、専門家が提案する書類の意味がすっと腑に落ちます。
ペットは“相続人”ではありません
法律上、ペットは“人”ではないため相続人になれません。そこで、飼養を引き受ける人(または団体)を受遺者や受託者に指定し、飼養という義務と資金管理のルールをセットで定めます。
遺言・負担付遺贈・ペット信託の使い分け
もっとも身近なのは公正証書遺言です。受遺者に「ペットを生涯飼養すること」を負担として課し、費用の支払い方法や監督者を明記します。資金を長期で段階的に使う設計やモニタリングを重視する場合は、信託(ペット信託)で「目的・支出・報告・後継受託者」を細かく定めると運用が安定します。
実務の流れ(はじめてでも安心)
初回相談では、飼い主の想い・ペットの年齢や性格・健康状態・かかりつけ医・緊急連絡網・預け先候補・資金源などを丁寧に洗い出します。そのうえで、家族の合意形成と法的枠組みを同時進行で整えるのが失敗しないコツです。
ヒアリングとプラン設計
飼養方針(食事、通院、散歩頻度、飼育環境)を具体化し、年間費用の概算、寿命見込み、予備費を計算。受け入れ先候補の意思確認も並行します。
書面作成と公正証書化
遺言・負担付遺贈・信託契約・死後事務委任契約などを整え、公証役場で公正証書化。鍵・通帳・保険・マイクロチップ番号などの情報管理リストも一式で作成します。
運用と見守り
年1回の内容見直し、連絡先の更新、受託者の健康・居住状況の確認、ペットの健康変化に応じた費用見直しをルーティン化。監督者(第三者)の設定で運用の透明性を高めます。
費用相場と専門家の選び方
費用は地域や案件の複雑さで幅があります。大切なのは“総額”だけでなく、運用時の手間とリスクをどれだけ下げてくれるかです。比較検討の際は、見積内訳と運用後のサポート体制まで確認しましょう。
費用の目安と内訳の考え方
初回設計・書面作成・公証役場手数料・信託登記等の初期費用に加え、見守りや年次点検の継続費用が発生する場合があります。飼養資金は「年間飼育費×残存年数+医療の上振れ+予備費」を基本式に、ペットの特性で増減します。
専門家の見極めポイント
実績事例の提示、動物福祉への理解、弁護士・司法書士・獣医師等との連携力、緊急時の一次保護体制、後継受託者の設計力、報告・監督スキームの透明性を確認しましょう。無料相談の段階で、あなたの“こだわり”(フード銘柄や通院頻度など)をきちんと文書に落としてくれるかも重要です。
よくある失敗と対策
口約束だけで資金手当がないと、引き受け先が見つからず困るケースがあります。制度と資金の両輪をセットにするのが対策です。また、受託者を単独にすると不測時に止まるため、後継受託者や監督者を必ず指定しましょう。
口約束だけで終わる
「家族が面倒を見る予定」でも、生活変化で続かないことがあります。必ず文書化し、資金と義務を明確にします。
受託者・受遺者の選任ミス
距離や健康、住環境を考慮し、バックアップ(後継受託者)を用意。団体に依頼する場合は、引き取り条件や医療方針の合致を事前確認します。
まとめ:今日からできる3ステップ
まず①年間飼育費と希望する飼養方針を紙に書き出す、②受け入れ先候補と事前に話し合い意思確認を取る、③専門家に相談して遺言や信託・死後事務を公正証書化する。この順で進めれば、ペットの未来はぐっと安心になります。あなたとペットの“いつも通り”を続けるために、今日から準備を始めてみませんか。